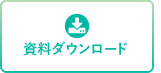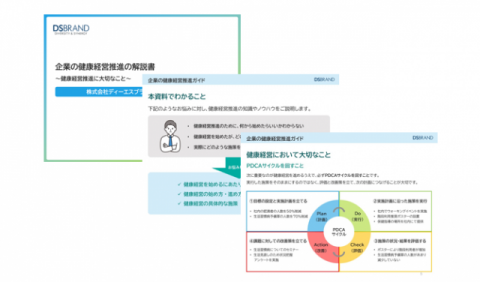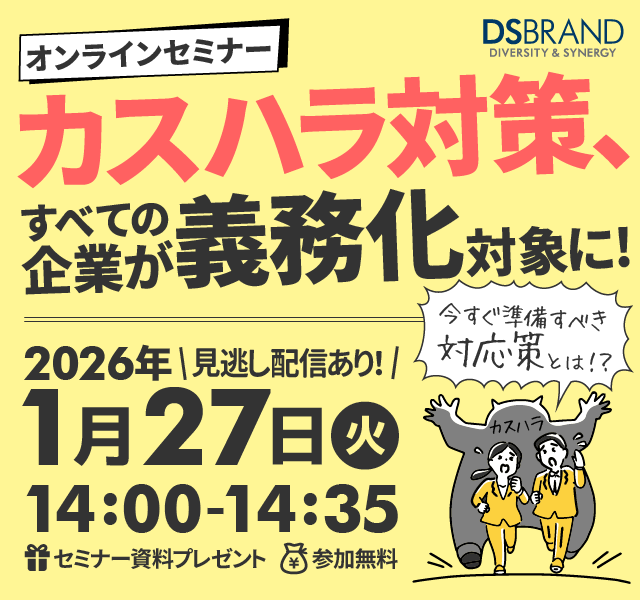- 「ストレスチェックってよく耳にするけど、実際どのような制度なの?」
- 「会社で実施したいけど、どのように始めたらよいかわからない・・・」
- 「ストレスチェックの義務化ってどうなっているの?」
このような疑問やお悩みをおもちの方のために、今回はストレスチェックについて詳しく解説します。
ストレスチェックの概要や、実施方法、実施義務などを中心に紹介しますので、自社へのストレスチェックの導入を検討している方はぜひ最後までご覧ください。
ストレスチェックの概要や、実施方法、実施義務などを中心に紹介しますので、自社へのストレスチェックの導入を検討している方はぜひ最後までご覧ください。
目次
ストレスチェックとは

ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
ストレスチェックを行うことによって高ストレス者を抽出し、メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防を講じられます。それによってメンタル不調者の発生を防ぎ、より働きやすく健康的な職場へと改善することを目的としています。
ストレスチェックの種類
ストレスチェックには紙ベースとWEB実施の2種類があります。
紙ベースはマークシート方式とそれ以外の2種類です。紙ベースは結果の集計が大変だというデメリットがあります。
WEB実施はURLもしくはQRコードでサイトにログインし、IDとパスワードを入力し受検するものが多いです。こちらは紙ベースとは違い、PCやスマホで受検可能な為、移動時間中や自宅での実施も可能になります。しかし、年齢層が高い職場だとうまくログインできずに受検自体を断念してしまうケースも多いです。
どちらにも一長一短があります。
また、項目数にも「23項目版」「57項目版」「80項目版」と3種類ありますが、57項目版は厚生労働省が推奨する「職業性ストレス調査票」でストレスチェックに必要な3領域を網羅しています。ちなみにストレスチェックは法令に定められている項目などは存在しないので厚生労働省ではこの57項目版を推奨しています。
ストレスチェックの実施義務について
ストレスチェックにはある条件を満たす場合に、事業者の実施義務があります。1つずつ説明します。
1.ストレスチェック実施の義務
2015年に労働安全衛生法が一部改正され、「ストレスチェック制度」が施行されました。そして、このストレスチェックは事業者にその実施が義務付けられています。対象となる事業所および内容は下記のとおりです。
- 対象となる事業所・・・常時50人以上の事業所。50人未満の事業所は努力義務。
- ストレスチェックの対象者・・・常時使用する労働者(※)
- 実施頻度・・・1年以内ごとに1回
※常時 50 名以上とは、契約日数・時間数に関わらず、継続して雇用し、使用している労働者をカウントします。継続雇用中である週 1 回程度のアルバイトやパート社員も含みます。
ただし、ストレスチェック対象者となるのは一般定期健康診断の対象者と同様ですので、正社員の週所定労働時間の4分の3未満であるパート社員や休職している労働者に対しては実施しなくても差し支えありません。
2.高ストレス者に対する面接指導の義務

ストレスチェックの結果は、検査を受けた労働者本人、実施者(※)および実施事務従事者(※)のみ知ることができます。
実施者から、本人に直接通知され、その結果「高ストレス者」と選定された労働者から申し出があった場合、事業者は産業医などの医師による面接指導を実施することが義務付けられています。
事業者は産業医の意見を聴取し、必要な場合は勤務時間を制限するなど就業上の措置を講じなければなりません。
ただしプライバシー保護のため、本人の同意なく、実施者から事業者に結果を提供することは禁じられていますのでご注意ください。
※実施者…ストレスチェックを実施する人。医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師など。
※実施事務従事者…実施者の指示を受け、調査票の回収・集計のデータ入力などを行うことで実施者を補助する役割の人。特別な資格は必要なく誰でも行えるが、ストレスチェック対象者の人事権をもつ者が実施事務従事者になることはできない。
3.集計・分析の義務

努力義務になりますが、事業者は、ストレスチェックの結果を受けて、集計・分析し、その結果に基づいた職場環境の改善の実施が求められています。
事業者は一人ひとりの結果の確認はできませんが、全体の結果を通して、職場のストレス状況を把握し、改善することで、1年毎にストレスチェック結果分析から、職場のストレス状況の変化をみることができます。
ストレスチェックはメンタル不調者の早期発見につながるとともに、結果をもとに職場全体の環境改善に努めることで、長期的観点から労働生産性の向上に繋がると報告されています。
これから導入する事業者向けに厚生労働者のホームページではスタートアップマニュアルや各種資料を公開しています。
役立つ情報が随時更新されておりますので是非ご一読ください。
ストレスチェック実施の義務対象が拡大?

これまではストレスチェック実施義務のある対象企業が、常時50人以上の事業所と定められていました。
しかし、メンタルヘルス対策の重要性が増す中、中小規模事業場におけるストレスチェック実施率の低さが課題となっていました。
しかし、メンタルヘルス対策の重要性が増す中、中小規模事業場におけるストレスチェック実施率の低さが課題となっていました。
そこで2025年5月、政府は「ストレスチェック制度を全事業場に義務付ける」という内容を盛り込んだ労働安全衛生法の法改正を国会で成立。早ければ2028年には、従業員数にかかわらず、すべての事業場でストレスチェックの実施が義務化される見通しです。
この義務化の拡大により、すべての事業場は年1回のストレスチェック実施が求められます。これに伴い、企業では以下の対応が必要となります。
- 実施体制の整備:ストレスチェックを適切に実施するための体制を構築する
- 従業員への周知:ストレスチェックの目的や意義を従業員に理解してもらう
- 結果の活用:集団分析を行い、職場環境の改善に役立てる
こちらは今後も動向をチェックする必要がありますので、厚生労働省などからの情報をこまめに確認しましょう。
ストレスチェックの実施方法
次にストレスチェックを実際に行っていく手順について詳しく説明していきます。
手順は大きく3つに分かれています。
1.実施前の準備
- 実施者と実施事務従事者の選定
ストレスチェックは前述した通り、実施者については医師・保健師または一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士を採用する必要があります。
企業の人事担当者や管理者が直接評価することはできません。これは実施結果の公平性を保つためです。
実施事務従事者に関しては、あくまでもストレスチェック実施の支援をする立場ですから、 企業の総務などからストレスチェック担当者を立てても問題ありません。
ただし、企業の人事に関わる従業員は従事してはならないとされております。
また、実施事務従事者が本人の同意なしにストレスチェックの結果にかかわることはありませんので、ご安心ください。
ただし、企業の人事に関わる従業員は従事してはならないとされております。
また、実施事務従事者が本人の同意なしにストレスチェックの結果にかかわることはありませんので、ご安心ください。
- 従業員への周知
ストレスチェックの目的や流れを従業員に対して説明し、受検は任意であると伝えなければなりません。
企業には年1回以上のストレスチェック実施義務がありますが、従業員に受検を強制することはできません。従業員の意思によって、受検するかどうか自由に選択できます。
また、個人の結果は本人の同意なく会社に提供されないことを説明し、安心して受検できる環境を整える必要があります。
2.ストレスチェックの実施

- 質問票の配布
一般的に厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」が使用されます。
質問は、ストレスの要因・ストレスによる心身の反応・職場でのサポートの3つのカテゴリーに分かれています。
企業によっては、独自の質問票を作成したり、簡易版(23項目)を使用したりすることもありますので、自社に合った方法で実施しましょう。
企業によっては、独自の質問票を作成したり、簡易版(23項目)を使用したりすることもありますので、自社に合った方法で実施しましょう。
参考ページ:職業性ストレス簡易調査票(57項目)
- 受検方法
紙の質問票:従業員が回答を記入し、封筒に入れて提出。
Webシステム:PCやスマートフォンからオンラインで回答。
3.結果の通知と対応
- 結果の通知
ストレスチェックの結果は個人に直接通知され、会社には本人の同意なしに提供できません。
- 高ストレス者の判定
ストレスの度合いが高いと判定された従業員(高ストレス者)には、医師の面接指導を受ける権利があります。
高ストレス者の基準については、事業場ごとに設定が可能ですが、一般的にはストレス反応がとくに高い人が対象となります。
- 医師の面接指導
本人の申し出をもって、医師による面接指導を実施できます。
医師は労働者の状態を評価し、必要に応じて、労働時間の短縮・休職・配置転換などの措置を助言します。
なお、この面接指導の結果は会社にも通知され、会社は必要な就業上の措置を実施する義務がありますので、実施前の段階で就業規則なども含め、体制を整えておくとよいでしょう。
4.集団分析と職場環境改善

ストレスチェックの結果に関しては、個人が特定されない形で集団分析を行い、職場のストレス要因を特定しましょう。また、職場環境の改善計画を立て、必要に応じて業務の見直しやサポート体制の強化を図るのも大切です。
5.結果の保管
ストレスチェックの結果については5年間保存する義務があります。個人情報として厳格に管理し、適切な取り扱いを徹底しましょう。
ストレスチェックはこのような流れに沿って実施する必要がありますので、ストレスチェックの義務化拡大に向けて各事業所で準備を行っていきましょう。
ストレスチェック義務化拡大は、近年中に実施される可能性が高い
ここまで、ストレスチェックについてご説明してきましたが、実際に義務化が拡大されるまでそこまで時間はかからないのではないかと予想されます。
つまり、自社でストレスチェックに取り組める体制を早く進めるのが非常に重要だということです。
ストレスチェックを紙ベースで行っている企業は全国的に非常に多いですが、結果の集計や分析を行うと考えると非常に手間がかかりますので、ツールを利用したストレスチェックがおすすめです。
ストレスチェックを紙ベースで行っている企業は全国的に非常に多いですが、結果の集計や分析を行うと考えると非常に手間がかかりますので、ツールを利用したストレスチェックがおすすめです。
弊社の健康経営ソリューション「おりこうブログHR」では、厚生労働省のテンプレートに則った「ストレスチェック機能」をご準備しています。実施者につきましてはご準備いただく必要がありますが、ストレスチェックの実施、集計、分析までをウェブ上で、一括で行えます。
また、ストレスチェックを実施し、高ストレス者と判断された場合は、「オンライン産業医相談機能」を用いて、産業医に直接相談することも可能です。
この機会にぜひ無料体験版や資料のダウンロードにお申し込みください。
この機会にぜひ無料体験版や資料のダウンロードにお申し込みください。